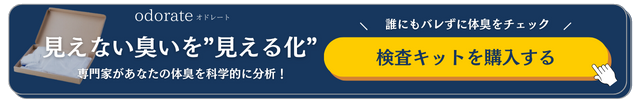「食生活が加齢臭に影響するって本当?」と疑問に感じている方に向けて本記事を書きました。
個人差はあるものの、食生活によって加齢臭が悪化・改善することがあります。
本記事では、「加齢臭の悪化原因になる食べ物」「加齢臭対策として有効な食べ物」「食べ物以外の加齢臭対策方法」をご紹介します。ご自身の生活を振り返りながら、読み進めてみてください。
▼加齢臭対策に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
加齢臭対策を講じても、あまり効果を実感できずに悩んでいませんか? 様々な記事で紹介されている加齢臭対策の中には、有効性が科学的に証明されていない方法や注意すべき方法があります。 例えば、加齢臭対策のためには生活習慣を見直すべきという意見があ[…]
加齢臭の原因は食べ物?

結論から申し上げますと、食べ物による加齢臭への影響は大きくありません。
食べ物が加齢臭の改善・悪化を部分的に促すこともありますが、食べ物は加齢臭の根本的な原因ではないからです。
加齢臭には、主に30~40代頃に発生する「ペラルゴン酸」によるものと、40~50代頃から発生する「ノネナール」によるものの2種類があります。時期やニオイの印象は異なりますが、どちらも皮脂の酸化などが原因で発生します。そのため、加齢臭対策としては、過剰な皮脂の分泌*¹を抑えることが重要です。
*¹皮脂には肌の潤いを保つ役割があるため、皮脂を過剰に取り除くと肌荒れが発生する可能性があります。
前述の通り、加齢臭の原因の大部分は年齢による体の変化です。故に、食生活だけが原因で加齢臭が発生している可能性は極めて低いのです。
しかしながら、食生活によって多少なりとも加齢臭が悪化・改善することもありますので、以下では「加齢臭の悪化原因になる食べ物」「加齢臭対策として有効な食べ物」と、根本策としての「食べ物以外の対策方法」をご紹介します。
加齢臭の悪化原因になる食べ物は?

動物性脂質や糖質は皮脂の分泌を促し、加齢臭の悪化を招く原因になります。しかし、摂取量を過剰に減らすと、かえって体調不良を招く原因になりますので、正しい知識を身に着けましょう。
動物性脂質の過剰摂取
加齢臭と動物性脂質の過剰摂取
脂質の1種である飽和脂肪酸*²を過剰に摂取すると、加齢臭を悪化させる可能性があります。なぜなら、体内に飽和脂肪酸が増えることによって、体外へ排出される皮脂の油分が増えるためです。
飽和脂肪酸*²とは…飽和脂肪酸は、炭素間に二重結合を持たない脂肪酸で、乳製品、肉などの動物性脂肪や、近年、我が国において使用量が増えているパーム油などの植物油脂に多く含まれています。 引用元:脂質による健康影響:農林水産省
飽和脂肪酸の目標摂取量
「脂質による健康影響:農林水産省」によれば、飽和脂肪酸の目標量は総エネルギー摂取量の約7%以下です。そのため、【総エネルギー摂取量×0.07÷9】の式を当てはめると、推奨される摂取量を導くことができます。※飽和脂肪酸1g=9calと計算した場合。
例えば、総エネルギー摂取量2000calの場合には、2000cal×0.07÷9=約15gですので、約15g以下の飽和脂肪酸を摂取することが推奨されます。
参考文献:「脂質による健康影響:農林水産省」
糖質の過剰摂取
加齢臭と糖質
過剰な糖質の摂取は皮脂の分泌を促すため、加齢臭の悪化を招く可能性があります。しかし、糖質は生きていく上で不可欠ですので、過度に摂取を制限すると健康に悪影響を及ぼします。1食の内で糖質を取らないなどの過度な制限は絶対に行わないでください。
糖質の目標摂取量
糖質の目標摂取量は規定しづらいため、目標摂取量は示しません。なぜ目標摂取量を示さないのか気になる方は下記の厚生労働省の資料をご参照ください。ただし、糖質を取りすぎてしまう方の特徴として、頻繁に糖質を多く含む飲料水や間食などを摂取している特徴があります。もし、心当たりがある方は、食生活を見直してみましょう。
参考文献:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書_各論_炭水化物
加齢臭対策として有効な食べ物は?

抗酸化食品は酸化を抑えるため、加齢臭の原因である皮脂の酸化を減少させると考えられています。ただし、過剰に摂取すると体に悪影響を及ぼしますので、正しい知識を身に着けましょう。
抗酸化物質とは、活性酸素を取り除き、酸化の働きを抑える物質のことです。活性酸素は微量であれば人体に有用な働きをしますが、大量に生成されると過酸化脂質を作り出し、動脈硬化・がん・老化・免疫機能の低下などを引き起こします。出典:抗酸化物質 – e-ヘルスネット
抗酸化物質は下記の栄養素です。
上記のリンクを押すと具体的な食べ物の紹介にとぶことができます。
ビタミンAと亜鉛
加齢臭対策として有効なビタミンAと亜鉛に関する情報を整理します。
ビタミンAの特徴
ビタミンAは、網膜細胞を保護するなどの役割を担っています。ビタミンAの欠乏は夜盲症など、過剰摂取は頭痛などを引き起こすことがあります。目標摂取量は、18歳以上男性は600~650μg/日、18歳以上の女性は450~500μg/日です。※(1μg=0.000001g)
ビタミンAは脂溶性ビタミンであるため、油と共に調理することによって効率的に栄養を得られます。
参考文献:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書_各論_ビタミン(脂溶性ビタミン)
ビタミンAを多く含む食品
ビタミンAを多く含む食品には、レバー類、バター、卵黄、にんじん、ウナギ、ほうれん草、ブロッコリー、トマト、モロヘイヤ、ピーマン等があります。
ビタミンAの効果を促す亜鉛
亜鉛はビタミンAの効果を高めると期待されています。そのため、ビタミンAと合わせて亜鉛も摂取すると良いでしょう。ただし、亜鉛の目標摂取量は成人男性11 mg/日・成人女性8㎎/日です。過剰に摂取すると、体調不良などを引き起こしますのでご注意ください。
参考文献:亜鉛 | Linus Pauling Institute
亜鉛を多く含む食品
亜鉛を多く含む食品には、牡蠣・ウナギ・あさり・レバー・カシューナッツなどがあります。
ビタミンCとE
体内でビタミンCとEが組み合わさることによって抗酸化作用が生じるため、加齢臭の対策を行う上でもビタミンCとEを摂取することが重要です。
ビタミンCの特徴
ビタミンCは皮膚や細胞のコラーゲンを合成する必須の栄養です。ビタミンCが欠乏すると、血管が弱くなり、出血が増えてます。一方で、ビタミンCの過剰摂取の場合には下痢などの症状が生じることがあります。ビタミンCの目標摂取量は成人男女共に100㎎/日です。ビタミンCは水溶性ビタミンであるため、水に溶けやすく茹でたり、煮たりするような料理には不向きです。
ビタミンCの参考文献:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書_各論_ビタミン(水溶性ビタミン)
ビタミンCを多く含む食品
ビタミンCを多く含む食品には、柿・キウイ・ブロッコリー・ピーマン・カリフラワー・青菜類・イチゴ・柑橘類などがあります。
ビタミンEの特徴
ビタミンEは様々な成分を酸化障害から守る役割を担っています。ビタミンEが欠乏すると脳軟化症や肝臓壊死、過剰摂取すると出血の増加などが起こります。ただし、欠乏や過剰が発生することは稀とされています。ビタミンEの目安摂取量は成人男性 6.5 mg/日、成人女性 6.0 mg/日です。ビタミンEは脂溶性ビタミンであるため、油と共に調理することによって効率的に栄養を得られます。
ビタミンEの参考文献:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書_各論_ビタミン(脂溶性ビタミン)
ビタミンEを多く含む食品
ビタミンEを多く含む食品には、ひまわり油・オリーブオイル・サフラワー油・コーン油・アーモンド・桃・スモモ・さくらんぼ・ドライトマト・ツナ缶・卵黄などがあります。
ポリフェノール
加齢臭対策として有効なポリフェノールに関する情報を整理します。
ポリフェノールの特徴
ポリフェノールは5000種類以上あり、ビタミンCやEに劣らない抗酸化作用があります。そのため、ポリフェノールを日常的に摂取するようにしましょう。様々な種類があるため、目標摂取量は規定されていませんが、過剰摂取は避けることをお勧めします。
ポリフェノールを多く含む食品
ポリフェノールを多く含む食品には、りんご・梨・ブルーベリー・ぶどう(ワイン)・チョコレート・緑茶・紅茶・玄米・生姜・大豆などがあります。
ミネラル類(セレン・銅)
ミネラル類に含まれるセレンや銅には、抗酸化作用があるため、加齢臭対策として有効です。ただし、過剰な摂取は身体に悪影響を及ぼしますので、摂取量に注意しましょう。
セレンの特徴
セレンは抗酸化システムや甲状腺ホルモン代謝において重要な役割を担っています。セレンが欠如すると、心筋障害を引き起こす克山病など、過剰摂取すると、慢性セレン中毒などが発症する危険があります。セレンの目標摂取量は成人男性30μg/日(耐容上限量450μg)、成人女性25μg/日(耐容上限量350μg)です。大量摂取にはご注意ください。
参考文献:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書_各論_ミネラル(微量ミネラル)
セレンが多く含まれる食品
セレンが多く含まれる食品には、マグロ・たらこ・かつお・全粒穀物などがあります。
銅の特徴
銅は成人の体内に約100㎎ほどあり、酵素の活性化やエネルギーの生成、鉄の代謝の役割を担っています。銅が欠如すると、貧血や白血球の減少などが生じることがあります。銅の最小摂取量は0.8㎎/日です。大量摂取は体へ悪影響を及ぼしますので、ご注意ください。
参考文献:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書_各論_ミネラル(微量ミネラル)
銅が多く含まれる食品
銅を多く含む食品には、牡蠣・イカ・タコ・レバー・納豆・ほたるイカなどがあります。
カロテノイド
カロテノイドの特徴
カロテノイドとは、動植物に広く存在する黄色または赤色の色素。大きくカロテン類とキサントフィル類に分けられ、強い抗酸化作用を持つ。カロテン類の代表的なものとしては、β-カロテンやリコピンなどがあり、β-カロテンは動物や人間の体内でビタミンAに変わります。引用元:カロテノイド e-ヘルスネット
このように、カロテノイドの抗酸化作用は加齢臭対策として有効です。カロテノイドの目標摂取量は規定されていませんが、過剰摂取は避けましょう。
カロテノイドを多く含む食品
カロテノイドを多く含む食品には、トマトやにんじんなどの緑黄色野菜・マンゴー・柑橘類などがあります。
食べ物以外の加齢臭対策方法
食べ物以外の対策方法をご紹介します。
- 入浴時に満遍なく体や頭皮を洗う
- デオドラント用品を活用する
- 衣服についた加齢臭の原因を洗い落とす
- 日焼け対策をする
▼加齢臭対策に関してさらにさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
加齢臭対策を講じても、あまり効果を実感できずに悩んでいませんか? 様々な記事で紹介されている加齢臭対策の中には、有効性が科学的に証明されていない方法や注意すべき方法があります。 例えば、加齢臭対策のためには生活習慣を見直すべきという意見があ[…]
あなたの加齢臭を専門家がチェックします

ご自身の加齢臭が周りの方にどのように思われているのかわからずに、一人で悩んでいませんか?
体臭評価キットオドレートを使用すれば、誰にも気づかれずに専門家による体臭評価を受けることができます。ご自宅でTシャツを24時間着用し、Tシャツを送るだけで、後日、結果がメールで届きます。ニオイの原因物質(揮発物質)26種類を9段階評価で専門家が教えてくれます。気になる方は下記のHPをご確認ください。
【まとめ】加齢臭と食べ物
最後までお読み頂きありがとうございます。
食生活によって加齢臭を改善・悪化させることがあります。しかし、過剰に制限したり、摂取すると体調不良や病気に繋がってしまいます。目安摂取量をもとに、ご自身の生活に合う対策法を講じましょう。
記事内でご紹介した以下の記事もお読み頂くことで加齢臭に対する正しい知識を身につけ、読者の皆さまが加齢臭を過度に心配することのない快適な日々を送るための一助になれば幸いです。
▼加齢臭対策に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
加齢臭対策を講じても、あまり効果を実感できずに悩んでいませんか? 様々な記事で紹介されている加齢臭対策の中には、有効性が科学的に証明されていない方法や注意すべき方法があります。 例えば、加齢臭対策のためには生活習慣を見直すべきという意見があ[…]
▼加齢臭に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
「自分の加齢臭が気になって、知人と会う時に不安を感じる」 「そもそも、加齢臭って何?」 「加齢臭の原因は生活習慣のせいなの?」 加齢臭を気にしすぎるあまり日常生活が不安ばかりになっている方がいると思います。 しかし、原因を理解せず、闇雲に対[…]